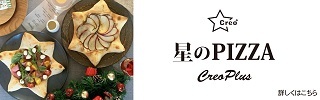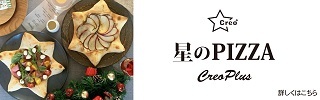先日、だいそれた挑戦をしてきました。
すなわち、昨年度私がお世話になった、三重県の森林インストラクター合格支援講座という連続講義で、一日講師を務めてきたのです。
もう募集は終了しておりますが、こんな講座です。
2023年度5月~9月 森林インストラクター資格試験合格支援講座(全9回)参加者募集中 – 三重県環境学習情報 センター
なかなか難しい試験である森林インストラクター資格試験は、独学ではもう相当にハードな試験ですが、森林インストラクター会三重は支援講座を頑張っている甲斐あって、順調に資格者を増やしている歴史があります。
私が昨年度無謀にも挑戦して、ギリギリの間に合わせであったものの合格できたのはひとえに講座のおかげさまなのでした。ひと通りの範囲を講師の言葉で説明してもらえて、五月後半から八月いっぱいの二週間に一度ペースで丸一日の授業があるので、それに合わせて嫌でも予習・授業・復習をしなければいけないので、絶好の機会です。そしてまた講座のときに疑問に思ったことやよくわからないことを質問して一緒に考えてもらうことで、独学ではできないほど理解が深まって力になるのです。
だから講師の役割はこの講座への恩返しということで、無事合格した者は次の人たちに道を示さなければならない仕組みなのだそうですが、体験談ならまだしもいきなり講師って、なんという荷の重さ。引き受けたものの途方に暮れたりもがいたり、或いはなかったことにしようとしたり、無様にモロにストレス受けていましたよ。
・森林の生態系
・森林の中のキノコ
・土壌と物質循環
この三つの科目を一日でこなし、質問があったら答えねばならないというハードな役目でした。それなりに準備はしたし、与えられた時間の間に話すことはいろいろあったものの、どうにもボロが出まくりで赤っ恥もいいところでした。お目付け役というか監督の森林インストラクター先輩が居てくれなければ到底乗り越えられなかったです。すみません、ありがとうございます。力不足な己に非がありますが、なんとか支えられて生きているのだなとまた強く感じることになりましたね。
そんなわけで講師としてお世辞にも立派と言えなかったのは謙遜でもなんでもなく間違いまくりの情けない私だったのですが、終わってから元気が出たというのが今回言いたいことなのです。
本当にストレスだけの嫌なことだったら、終わってからぐったりします。
気が乗らない会議とかやたら人の多いイベントとか、もう滅多にありませんが接待的な飲み会とか、ああやれやれといった疲れだけが残るものです。
これもそうかな、役目を果たしたらもういいかなと思っていたのですが、本当に意外にも終わってからエネルギーが満ちてきた体験になったのです。

教える価値があることを知っていたんだね
ああ、私はこんな感じで教える役割が好きなんだと気付きました。以前から人前で話すことは抵抗がなかったですし、好きに話していい講演は得意な気はしてましたが、ただ楽しい話し手というのでなく講師の立場も好きなのでした。伝えることが好きで、もっと深くやりたいことなんだなと実感できたのは大きな発見でした。せっかく森林インストラクターという資格をとったものの、自己満足で終わったらどうしようと心配だったのですが、活かすための挑戦を続けていけそうです。
まだ実績も信頼もないただ「豊かな自然環境で暮らす、生き物が好きなだけのおしゃべりおばさん」が環境教育の講師として活躍していく道筋はちっとも明確に描けやしないのですが、講義中に話をしていて、私が今まで蓄積していた自然や生き物との関わりはものすごい源泉になっているということを実感しました。獣や鳥、虫に草木や土壌のことを、辞書レベルではないけれど事典並には話せるかもしれません。抜けは多いですが幅の広さはなかなかで、そんな人はどこにでも居るわけではありません。
私、できる、そんな静かな自信が沸々と波打ってきました。
人生をご機嫌に生きている人が以前おっしゃっていたことで印象に残っているセリフの一つに
「やる前とやった後で元気になることを増やしていくことが大事」
というのがあります。
自分の日常や予定の中で、やった後疲れちゃうものをできるだけ減らしていって、やった後元気になるものの量をできるだけ増やしていくことをめちゃくちゃ意識するといいというアドバイスでした。それを信じてブログを書くことは優先して続けておるのですが、書くことの他に、伝えるために話すことも私を元気にしてくれます。
森林と生き物の関りをまるごと優しく伝えたい。
細かい木の名前はまだまだわからないけれど、人と関わりのある木とは少しずつ親しくなっていて、農山村の歴史と共に時間をつなげていきたい。
環境教育というまだよくわからない分野をできるだけ楽しいイメージで広めていきたい。
そしてその全てが大好きな環境の保護につながるといい。
うん、願いはこんなかんじなので、元気になるはずですね。
森林インストラクター会の活動として、夏休みにいくつか授業のお手伝いの話があります。実際に先輩方がどんな仕事をされているのか身近で学べる大チャンスです。
ストレスを乗り越えた先のこれからのチャンス。楽しんでいきたいです。
楽しそうなことをするのがこれからの生き方ならば、私は森林教育に関わっていきたいですし、いろんな人がいろんな好きなことができたらいいですね。
そんな一つが下のこれですね。星形ピザって夢がある。人につながっていく楽しみを生み出す人って素敵ですね。どうぞ乗っかって楽しんで下さい。